2017年7月13日 第28号
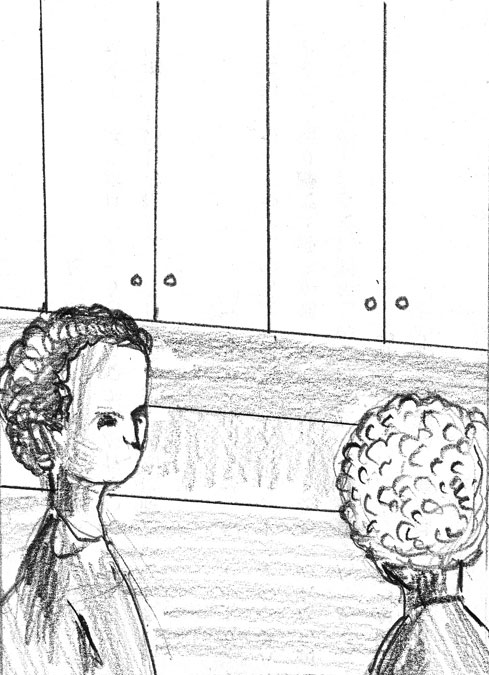
イラスト共に片桐 貞夫
「じゃあ、どういう動機でどうなったかも判らないのね」
「まだなにも言えないと言って、なんにも言ってくれないの」
「じゃあ警察は、殺人らしいということだけを言いに来たのね」
「人間関係を訊いたわ」
「友達ね」
「でもなんにもないの。ジェニファーは人に好かれる子だったから友達はいっぱいいたようだけど、特に親しい人はいなかったと思うの」
「そう? それに二十年も前のことだからわからないわよね」
「そうなの。でも警察は手紙を持っていったわ。ジェニファーから来た手紙をみんな」
「あ、手紙が残っていたのね、ジェニファーからの」
「そうなの。ジェニファーの思い出なの。…ウウウ…」
自分の言葉にステイシーがまた泣いた。
そのとき蘭子は、他にもジェニファーの写真が飾ってあることに気がついた。リビングだけで四枚ある。それぞれ少女期のものから高卒の時までのもので、いかに可愛がられていたかが歴然であった。
九、
その晩、蘭子はクリニックで体験したこと、また、隣家で聞いたことにはいっさい触れずに輝昭とクリスティーンに接した。そして翌朝、輝昭が出勤し、子供たちが野外で遊びだしたのを見届けてからクリスティーンに訊いた。ティーカップを片手に、なにげなさを装った。
「ねえ、クリスティーン、訊きたいことがあるの」
クリスティーンは口数が少なく話しづらいが、話しかけると飾言なくものごとを言い、その点、蘭子は好感を持つようになっていた。
「どうしてこの家を買うことになったのかしら」
ジェニファーの実家のすぐ隣である。
まさかとは思ったが、輝昭はジェニファーと同時期にブリティッシュ・コロンビア大学に行っている。輝昭の不可解なマクマスター大学への転校と、ジェニファーが「殺害」というかたちで二十年まえに死んでいるということが気になって、蘭子は眠れない夜を過ごしたのだった。
「この家のこと? 知らないわ。わたしが知り合ったころ、テルアキはもうこの家に住んでたんだから」
「それは分かるけどなにか聞いたでしょう?便利だからとか古い家が好きだからとか。高いお金を出して買ったんだからそれなりの理由があったはずよ」
「しらないわ」
「そう、なにも聞いてないの?」
「ええ」
「前の通りがうるさくて、子供を育てるには理想的なところじゃあないのに、どうしてこの家に決めたのかしら輝昭」
「わたしは好きだわ、この家が」
蘭子が不満だらけでもクリスティーンは文句を言わない。いや蘭子は、クリスティーンが苦情を言っているのを見たことがなかった。
「わたしねえクリスティーン、輝昭とは年に一度しか会えないでしょう。だから分からないことがいっぱいあるの」
蘭子は懸命に言葉を続けた。喋っているうちにクリスティーンの口からなにか出てくるかもしれないと思ったのだ。
「クリスティーン、あなた、輝昭がバンクーバーのブリティッシュ・コロンビア大学にいたっていうことをしらなかったって言ったわね」
「ええ」
「でも一緒に暮らしていて、輝昭、なにか言わない?」
「なにかって?」
「マクマスター大学に来たことよ」
「言わないわ。わたしはなんにも知らないの」
「そうなの? チャッドは、二十年まえはブリティッシュ・コロンビアの医学部のほうが上だったって言うし、輝昭はバンクーバーがすごく好きだったから、トロントに来た理由が分からないのよ」
二十年前とはジェニファーが行方不明になったころである。
「……」
「輝昭、なんでトロントに来たのかしら」
蘭子の口調がひとりごとのようになっている。
「ドクターに憧れたからじゃない?」
「ドクター? ドクターエーデルマンのことね。わたしもそう思ったわ。でもねクリスティーン、輝昭がドクターのことを知ったのはもっと後のことなのよ」
「そう?」
「じゃあクリスティーン、隣のジャックとステイシーだけど、輝昭はここに越してくる前から二人のことを知っていたのかしら」
「知らないわ。テルアキに訊いてみるわ」
(続く)












