2017年3月23日 第12号
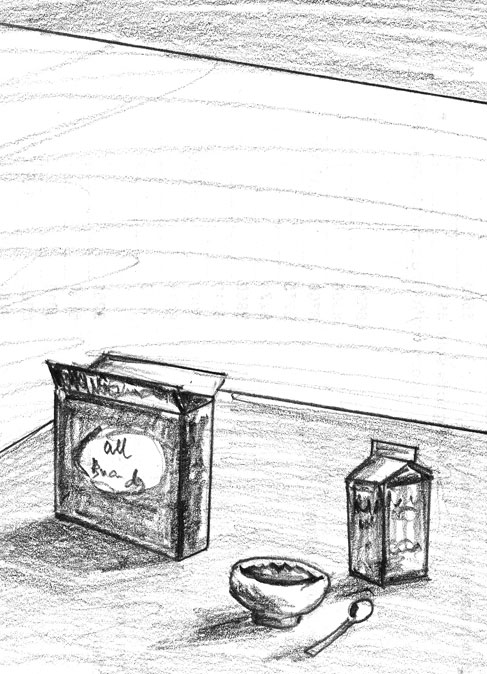
イラスト共に片桐 貞夫
「あたしの買ってきた半そでのシャツを着ればいいのに。トロントの夏は暑いっていうから、いちばん涼しそうなのを買ってきたのよ」
「わかってるよ。でもジョギングに新品着ることないだろう」
「だって、そんなに汗かいて。新品っていったって、あれ、そんなに良いものじゃあないのよ」
「でももったいないよ」
「あんた、なによ、医者のくせに。いないわよ、そんな古くさいシャツを着てる人なんて、日本に」
ジャージは色があせて袖口がほころびている。
「俺はこれが好きなんだ」
「だって…」
蘭子が、あたりの粗末な家具を見回して不満そうに言葉を詰めた。
建石蘭子がカナダはトロントの郊外で開業医する輝昭宅を毎年のように訪れるようになったのは、やはり医者であった夫に先立たれた十三年前からのことであった。蘭子には、他に六才年上の長男と三才年上の娘がいて、それぞれ日本でつつがない生活をしていたが、家庭の異端児のようであった末っ子の輝昭を蘭子はこよなく愛した。勉強好きで従順な上二人に較べると輝昭は向こう意気が強いくせに甘えん坊で、上二人が一年早々で乳離れしたというのにいつまでたっても添い寝をねだり、蘭子に抱きついて寝るのが好きだった。死んだ夫が、この子に貰われるお嫁さんは幸せだぞ、と、よく冗談を言ったものである。
輝昭は、慶応大学を一年終えたとき、高校時の夏季ホームステイのコネからカナダに留学した。バンクーバーはコロンビア大学の医学部に入ったのだ。アウトドアスポーツの好きな輝昭は海と山に包まれたバンクーバーという都市を無上に好み、住み出して三カ月もしないうちに永住を匂わせることをなんども言った。ところが、大学生活1年目にしてトロントに移った。トロントのマクマスター大学に編入したと、いきなり電話で言ってきたのだ。意表をついたのはそれだけでなかった。当然父親の轍を踏んで外科に進むと思っていたのに産婦人科に進んだ。輝昭は父輝和の反対の甲斐もなく、マクマスター大学の産婦人科を卒業したのであった。
「お腹すいた?」
輝昭が立ち上がって蘭子に訊いた。
「そうねえ。あんまり空いてないけどなにか食べなくちゃあねえ、朝なんだから」
蘭子の言葉が歯切れ悪く詰まった。蘭子は時差ぼけもあって食事が苦手であった。いや、食べるのは好きなのであるが、この輝昭宅の食事が喉を通らない。キャンプや山登りをよくした輝昭は料理が得意で、かなりのものができるはずだが、このテーブルの上に出てくる野菜や肉は、熱こそ通っているが調味というものがされておらず、日本人の常識から見ると、かなり原始的なものであった。家人の子供までもが適当に適量の「食物」を皿に載せ、ケッチャップとソースで味付けをして食べるというものであった。
「ね、今朝は私にやらせて」
蘭子が立ち上がった。朝食を作るという意味である。
「いいよ。それより母さん、シリアル嫌いなのか」
「シリアルって…ミルクを入れて食べるの?」
「うん。パンもあるけど、普通カナダでは朝はシリアルを食べるんだ」
「ベーコンとか卵は?」
「うん。そういうものも食べるけど、普段は面倒なんでシリアルになっちゃうんだよ」
「面倒っていったって…あたしがやるわよ」
蘭子が冷蔵庫の方に歩いた。
「ないんだ。ベーコンもエッグも切らしちゃってるんだよ」
「あら…」
蘭子は腹の中で声を上げた。かなり大きい冷蔵庫なのにベーコンがない、卵がない。いったい何がこの中に入っているんだろうと蘭子は思った。
「お米あるんでしょう? あんただってたまには納豆とか漬物でご飯食べたいでしょう?」
蘭子はかなりのみやげを持ってきたが、その内の半分は食料であった。その一部を使って日本風の朝食にしようと思ったのだ。
「納豆か。納豆、あげちゃったんだよ」
「あらそう。あげちゃったの」
「そうなんだ」
(続く)












