2017年3月16日 第11号
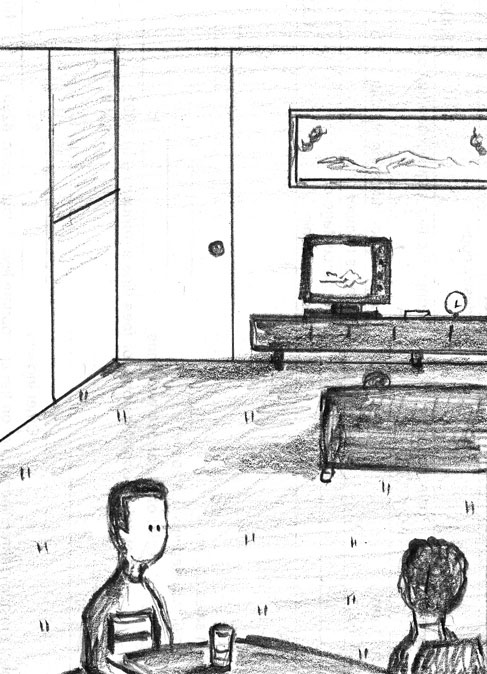
イラスト共に片桐 貞夫
「そうなんですよ。バンクーバーも、もう良き時代は終わりました」
「でも、その容疑者が二十六人の人間を殺したっていうことは事実なんですね」
「そうでしょうね。この容疑者は六十を過ぎた男なんですが、親の代から今の土地に住んでいるそうですし、女の骨が出てきたんですからね」
「そうですか。そんなひどい事件が起こっていたんですか、あの美しいバンクーバーで」
「もう昔の良きバンクーバーはおしまいですよ」
男が新聞を妻に戻して言った。
機内放送が、飛行機はこれからロッキー山脈にかかると告げていた。
二、
「なんだ母さん、起きてたの?」
建石輝昭が裏口から入ってきてそっと言った。ジョギングで顔が汗で光っている。
「おかえりなさい」
キッチンのテーブルに座っていた蘭子が嬉しそうに顔を上げた。
リビングの一角で、黒人の幼い女の子がパジャマ姿でテレビを観ている。建石輝昭が少女に英語で言った。
「ジョージエット、ポールたちはまだ寝ているのか」
「うん」
少女が振り返りもしないで大きくうなずく動作をした。
「ジョギングってこんなに長くするもんなの」
蘭子が訊いた。誰もが声を抑えている。
「いや、今日はいつもと違うところまで足を伸ばしたんだ」
「せっかくの日曜日だっていうのに」
輝昭の毎朝の忙しなさに、蘭子は日曜の朝を楽しみにしていたのだ。
「ごめんごめん、母さん寝てると思ったから。きのう遅かったし、だってまだ八時前だよ」
「寝てなんかいられないわよ。車はうるさいし、時差ボケだし」
輝昭の家はかなり交通量のはげしい通りに面している。
「じゃあ、ずいぶん前から起きていたのか」
「そうなのよ。ちゃんと、三時になると目が覚めちゃうんだから」
「まだ時差ボケやってんのか」
言いながら輝昭は蘭子の座る前を通ってキッチンの流しに行った。水をコップに注いで飲もうとした。
「あらちょっと。カナダの水って飲めるの? だめよ水道の水なんか生で飲んじゃあ」
「へいきだよ」 輝昭が笑ってコップの水を飲み干した。
「あらどうしたの」
輝昭の両手が汚れている。膝にも泥が付いている。
「ねえ、転んだの? 怪我しなかった?」
「いやいやそうじゃないんだ。ちょっと庭仕事を手伝ったんだ。ジョギングの途中で庭石を動かすのを手伝ったんだよ」
「庭石を? こんなに早く?」
「うん。いつも通るところに早起きの夫婦がいるんだ。年寄りなんだよ」
「あんたってまだそんなことを」
蘭子が哀れむかのような顔をして輝昭を見た。輝昭はいつも同じようなことを言う。人に異常に親切なのだ。
「そんなこともなにもないよ。大したことじゃないんだから」
「だって赤の他人でしょ」
「ま、そうだけど、いいじゃあないか」
「日曜ぐらい、ジョギングなんか行かないで寝坊してればいいのに」
「寝坊していられないたちなんだ。それに、ここは四時前から明るくなっちゃうんだよ」
「わかってるわよ。それにしちゃあクリスティーン、よく寝るわね。まだ寝てるんでしょ」
蘭子は、「日本からのお客さんがいるっていうのに」と皮肉を付け足そうとして口を押さえた。クリスティーンというのは輝昭の妻である。
「いくら寝たっていいだろう。金がかかるわけじゃなし」
「だって主人のあんたが起きてるっていうのに」
「ほらほらほら、だめだよ母さん忘れちゃあ。ここはカナダなんだから」
「そうそう、そうだったわね」
蘭子が口もとだけを笑わせてうなずいた。
輝昭が汗をふきながらふたたびグラスに水を注いでいる。
「ねえ、なんかないの? レモネードとかアイスティーが」
「ないんだよ」
水を飲み干した輝昭が笑って言った。
「そんなもん脱いじゃえばいいのに」
輝昭は半ズボンこそはいているが上半身は長袖のジャージである。
「うん。いやへいきへいき」
「あんたは汗っかきなんだから脱いじゃいなさいよ」
「へいきだよ」
(続く)












