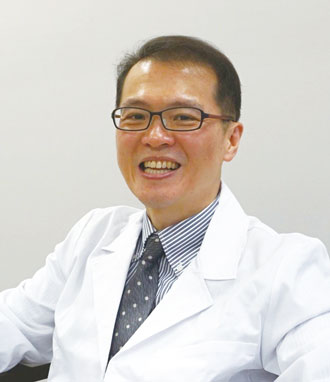2018年8月2日 第31号
前回の特集に引き続き、アトピー性皮膚炎における「本治」の各種漢方薬を紹介する前に、緩やかな効目こそ漢方そのものだと理解していても、やはり「即効性」を求める患者の思惑について視点を変えて探求してみる。何方でも病気になって、医者通いをした以上、なるべく早く癒されて、悩ましい症状から解放したい気持ちがあるので。臨床上、「症状に合った漢方薬を医者に処方してもらったが、飲んでも目に見える効果が出ない」という、うまくいかないケースもしばしば遭遇される。
患者としては、医者と真摯にコミュニケーションを取ることがもちろん大切。漢方医はこういうことに直面する時に、まず、肝心な「証」の診断が問題ないかどうか。東洋医学の領域で特に「気、血、津液」による体質診断が重要で、更に各内臓毎に細かく分類することで、やっとある「証」に辿り着く。場合によって、患者それぞれの症状や訴えが曖昧で、丁寧に診察しても納得できる「証」がどうしても帰結しにくい例もあり得る。医療の世界では、「患者さんが教科書通りに病気にならない」とは常識で、そのため、漢方医の知識や経験も問われ、医者にとって日々が修行かつ挑戦、人によっては当初期待している成果を上げられないこともある。しかし、服用して効果を見ながら内容を変更するという柔軟性も漢方診療の特徴の一つ。使ってみて効果が薄ければ効能の高い他種漢方薬を加味したり、逆に症状が悪化すれば作用機序の違う漢方薬に変えてみたりすることも考えられる。医者と患者相互に信頼関係を築くのにお互いの努力が不可欠で、すぐに諦めずに、根気よく患者の体の状態に合ったものを模索していくのが最善策だと思われる。
なお、「飲むのをやめると、飲んでいたときよりも楽になる」、もしくは浮腫み、体重の増加、眠気などの不調に陥る場合、漢方薬が身体に合わないかもしれないという結論付けになる。それは珍しい事ではなく、人間の体に合わない食品はあって当然なことで、例えば、各人種には一定の割合で小麦のグルテンや、牛乳の乳糖に耐性がない人もいる。因みに、食品に対する耐性のなさは程度に差があるものの、苦手な人が統計上一定数を占めている。漢方薬に合わない人ももちろん存在する。
さて、引き続きアトピー性皮膚炎に用いる「本治」の漢方薬の話を少しする。「本治」こそ実に漢方診療の醍醐味。患者さんの体全体の調子が良くなるにつれて、皮膚の症状も徐々に改善されることが漢方医冥利に尽きるところである。
まず前回も紹介した本治の代表的漢方製剤は「補中益気湯」。柴胡、升麻、甘草、黄耆、人参、生姜、大棗、陳皮、当帰、蒼朮からなる名方剤。陰虚証、気虚となる患者にエネルギーを補う代表的な製剤。全身倦怠感や食欲不振、消化機能が衰え、気力低下、言語や眼の光に力がなく、顔色不良を伴う虚弱体質、慢性疾患患者の体質改善剤との定評がある。その免疫調整作用によって、アトピー性皮膚炎において,好酸球数・血清I g E値減少作用及びTh2優位状態抑制作用、ステロイド・タクロリムス外用減量効果が報告されている。つまり過剰なアレルギー反応を抑える作用が期待でき、バランスよく安定した身体の免疫状態をもたらしてくれることで、湿疹ができにくくなり、掻痒感も薄らいでいく。筆者の経験では、アトピー性皮膚炎だけに止まらず、帯状疱疹を患った後全身倦怠感を伴う患者には、早期に補中益気湯の投与で早く体力の回復につながる症例が少なくない。
次に、冬季の厳寒時期に、体力を付けるためによく使われる定番の「十全大補湯」。昔から漢方薬局には必ず備えられている名方剤。白芍薬、茯苓、甘草、地黄、黄耆、人参、桂皮、川芎、白朮、当帰からなる十全大補湯は、補血薬の四物湯と補気薬の四君子湯の合方「八珍湯」に黄耆と桂皮を加えたもの。気血がともに衰えた場合に対して、気を補い、陽を温める力を持ち、陽が生まれ、陰が育つを目標とした大いに補する製剤である。例えば、大きな手術を受けた後或いは慢性疾患などで、全身倦怠感、食欲不振、顔色不良、皮膚乾燥、貧血、盗汗、口内乾燥感などを伴う場合に一般的に使われる。アトピー性皮膚炎では、気力・体力が低下して冷え症(末梢循環不全、手足が冷たい)になっている体質改善の方剤として使用される。現代薬理学的な研究では、この十全大補湯には、免疫賦活作用、体重減少抑制作用、放射線障害防護作用もあるといわれている。
ここで余談になるが、漢方薬成分の「人参」は日常食べる野菜類の“ニンジン” (セリ科の根菜、“胡蘿蔔”、こらふとも呼ばれる)とは違うもの。漢方薬の人参はPanax ginseng 、ウコギ科の多年草、オタネニンジン(チョウセンニンジン)の根で、健胃、強壮作用、代謝促進、免疫賦活作用などを有する。人参を含む方剤はかなりの数で、主に胃腸症状や疲労倦怠感を訴える虚証の患者に用いられることが多い。古来、王侯貴族に愛用され、封建王朝や宮廷文化に馴染むアジア系の人々が好む体を強める補剤として有名な薬。江戸時代には、大変高価な生薬なので、庶民には高嶺の花。これ故に、分不相応なほど高額な治療を受けることを戒める「人参飲んで首括る」の諺も生まれた。「人参で行水」は医薬の限りを尽くして治療をすること。
医学博士 杜 一原(もりいちげん)
日本皮膚科・漢方科医師
BC州東洋医学専門医
BC Registered Dr. TCM.
日本医科大学付属病院皮膚科医師
東京大学医学部漢方薬理学研究
東京ソフィアクリニック皮膚科医院院長、同漢方研究所所長
現在バンクーバーにて診療中。
連絡電話:778-636-3588