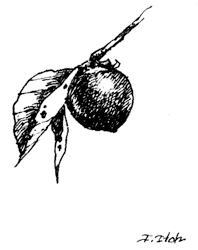
六十年代のはじめ。世の中に飛び出して間もない頃、東京・東銀座にあった老舗の広告代理店につとめて、青くさいデザイン論に明け暮れていた。
ある秋のこと同僚のY君がやってきて私を旅にさそった。聴けばY君の祖父母が山梨県の身延の山裾に住んでいて、猪も出るような草深いところ。その祖父母の家に泊めてもらうと云う。
都心の騒音のまっただ中で仕事をしていた毎日だから私はこの話に飛びついて、他の同僚二人と一緒に連れていってもらうことになった。男四人の小さな旅だった。
安月給をはたいて買った白っぽいフラノの背広を着てその山裾の家に着いたのは、そろそろ甲斐の山に陽が落ちる夕暮れ。小さな茅ブキの農家がひっそりと佇ずんでいた。
家の裏手は山で山菜の宝庫だった。ワサビが山から湧きでる水の中に密生している。毎年、何頭かの大きな猪が里を荒らしに降りてくるそうだ。当時、池田内閣が掲げた所得倍増論などとは、およそ縁のない世界がそこにあった。
高齢のY君の祖父母に案内されてはじめて茅ブキの家に入った。時代を感じさせる黒光りした柱、ギシギシ音を立てる板の間の炉端。どれを見ても都会ではもう見られなくなった日本の原点の姿だった。
台所を見に行ったY君が戻ってきて「今夜はトリ鍋をやってくれるらしい」と云う。炉端で持参した安いウィスキーを啜りつつ、燃える薪の煙に目をしばたたきながら吊られた鍋をご馳走になったのはそれから間もなくだった。
土地の古老が話す山里の暮らしは普段、雑踏の中で生活している人間には想像以上に厳しく感じられたものの、一方で日本昔ばなしを聴くような懐かしさがあって、かすかなあこがれを抱かせる。
全く音がない山里の夜ー。翌日は土地の名勝、見延神社に詣で日頃の都会暮らしの汚れを落し、身も心も清らかになった我々は一宿一飯のお世話になった茅ブキの軒先でY君の祖父母に別れを告げる。もう明日は、又あの人の波の中で働く生活が待っている。
小さな庭を見渡した。この貴重な体験を心にとどめようと思った。きのう覗いた軒先のウサギ小屋を見た。夕べ、一匹しかいないウサギがジッと赤い目で一点を見つめて鼻をモグモグ動かしていたのに見当たらない。
たしかツガイで飼っていたウサギの雌が亡くなって残った雄だと聴いた。
嫌な予感がしてY君にきいた。
「どこか他の場所に移したんじゃないの…」さして気にもせず、Y君がおじいさんに聴いている。
もう九十歳に手が届く朴訥なおじいさんの顔に一瞬はずかしそうな表情が浮かんだのを私は見逃さなかった。
「夕べの鍋だってヨ…」とY君が顔をゆがめて笑う。
予感が適中してしまった。
鶏だと思ったあの柔らかい肉は、あのヤモメ暮らしのウサギだった。
思えば決して豊かとは云えない山里の古老夫婦の暮らしである。都会から訪ねてくれた孫Y君と、その友人たちに精一杯の心づくしのもてなしをして下さったのだろう。
四人の浮かれた生意気盛りの若僧はそれをきいて途端に静かになってしまった。
庭に一本の柿の木があってたった一つの渋柿が残っていた。私はその下で夕べの兎を偲んでその柿を見上げていた。その時あろうことか、その赤く熟した最後の柿の実が私の白いフラノの背広に落ちた。風も無いのに…。
その時以来その赤いシミはいくら洗ってもとれなくて着られなくなった。
あのヤモメ暮らしの兎の目の色が私の背広に最後の別れを残したようで不憫だった。
帰りの中央線の列車。ボックス席に座った四人は元気がなかった。どうしても夕べ食べてしまった兎のことが頭を離れない。まるで都会から悪事を働きにきた悪者のような罪悪感が抜けない。
いつも陽気な制作部のM君がチビチビ、ポケットウィスキーを飲みながらY君をなじる。
「お前たしか鶏ナベだと云ったよなあ…可哀そうなことをしたなあ…」上目づかいにY君の顔を見る。
「しょうがないじゃネエか、もう喰っちゃったんだから。いつまでグスグス云うんじゃネエヨ!」とY君。
「何しろあのウサギはヤモメ暮らしだったんだからなあ…それを喰っちゃったんだからなあオレ達は…罪は重いヨ…」呟くように営業のK君が云う。
列車の窓から見る景色は実りの秋、黄金の波だった。
あしたから又、東銀座の騒音の中で唯々、前に向かって走り続ける生活が待っている。
一人(匹)暮らしの兎を胃袋に収め、渋柿に鉄槌を下された心の痛みは多分三日もすれば忘れてしまうのだろうと思った。
分が悪くなったY君は揺れる列車に身を託して狸寝入りをしていた。
2010年5月6日号(#19)にて掲載












