2016年12月1日 第49号
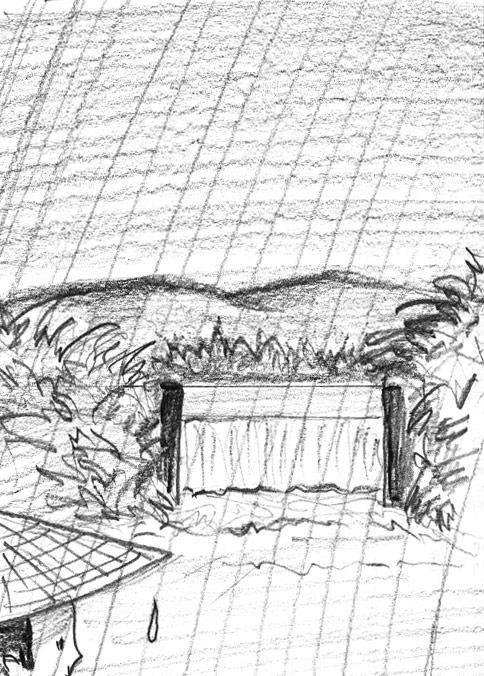
イラスト共に片桐 貞夫
「喰われたっていう仏さんは誰なんです。どこの女なんです」
「豊田村の久八っていう百姓の娘よ。まだ十六になったばかりの器量好しだ」
「誰が見つけたんです」
「ゴンゾウとかいったっけな」
「上田村のお百姓ですか」
「そうよ。そいつが滝つぼの池に浮いてる女の身体を見つけたんだ。とにかく、あの滝の上を登って行きゃあ、あのバケモノのすみかだかんな」
文吉は、栄助が染谷川上流の山中に住んでいたことを言っている。女の死体がそこから流れてきたと意味している。
「下手人がそうだとするとその男、どうしてせっかく手に入れた得物を水に流しちゃったんですかねえ。全部食べちゃえばいいのに」
「なにー」
「これじゃあ、わざわざ俺がやったんだって言ってるようですよねえ」
「なんだとぉ」
文吉がリュウをにらみつけた。
「じゃあ、そのゴンゾウさんとかは、なんで滝なんかに行ったんですかね、こんな天気に。用でもあったんですか」
「池の堰板を外すのをたのまれたそうだ」
「たのまれた? 誰に」
「決まってるじゃねぇか、名主のかみやよ。そんで行ってみたら、女の白え身体が浮いてたんだよ」
「喰い殺されてたっていうことですけど、仏さんはどんなだったんです?身体のどこかが喰いちぎられていたんですか」
「いや、そりゃおめえ」
文吉は二度ほど首を振ってから口をつぐんだ。そして額にたて皺をよせてリュウの顔をのぞき込んだ。
「おい、くじら。おめえやたらと訊くじゃねえか。なんだってそんなこと訊くんでえ。…えっ?」
「いやですねえ親分。あたしだって女ですよ。喰い殺されないようにと思って訊いてんのよ。おお、こわ」
「そりゃそうだな。でも、もう心配ねえ。あのばけものも、あと三日もすりゃしおき送りだ。分からねえぜ何人食ったか。あのあたりじゃ、よく女がいなくなるんだ」
「おおこわ」
リュウが襟元を合わせて背を丸めた。
リュウは、サキの父富次の二人の妻が失踪したことをふと思った。
「おおこわおおこわ。…ところで親分、どうしてあの男が殺したって判ったんです? 口がきけないんでしょう」
「しつっけえなぁお前ぇは。あの化け物が喰ってるところを見た奴がいるんだよ」
「喰ってるところを? おかしいじゃないの。だって、ゴンゾウさんが初めて滝壺で仏さんを見つけたんじゃないんですか。喰ってるところは誰が見たんです。いつ見たんですか。山の奥でですか」
「うるせえ!」
文吉のダミ声が割れた。
「くじら! お前ぇなにしに来た。ここになにしにやって来ゃがったんだ。こんな狸の小便みてえな安酒ばっかり飲ませやがって。判かってんだよ! あのバケモノが喰ったってえこたぁ上田の小せえわっぱまでもが知ってんだ。失せろ! とっとと失せやがれ!」
リュウがゆっくりと立ち上がった。荒れる文吉を無視して首をかしげて出ていった。
三
はなしの筋書きに無理が多すぎる。栄助犯人の証拠はないし、証人がいるとも思えない。死体を見ていないのでわからないが、喰ったという事実もあやしいということだけが分かってきた。ただ簡朴な村人たちの目に裸に剥かれた女の無惨な死にざまと、一人、山に棲む異形の栄助が必然的に結びついた。食いちぎられた死体と、発見された場所が染谷川ということで、栄助を犯人にこじつける偏見が生じたように思えてならなかった。
右手に倉田の田どころを見、山際に沿うかまくら道を戸塚から一里ほど行くと、妙願寺の塔が飛び出す杜が見えてくる。その手前を染谷の川が横切って、二本の丸太が橋になっていた。少し勢いをつければ飛び越えられそうな細い川だが、降り続ける雨で奔流となり、跳沫が丸太に当たって音をたてている。かみやの屋敷はその川の脇を左に入った小高いところにたっていた。
(続く)












