2018年1月18日 第3号
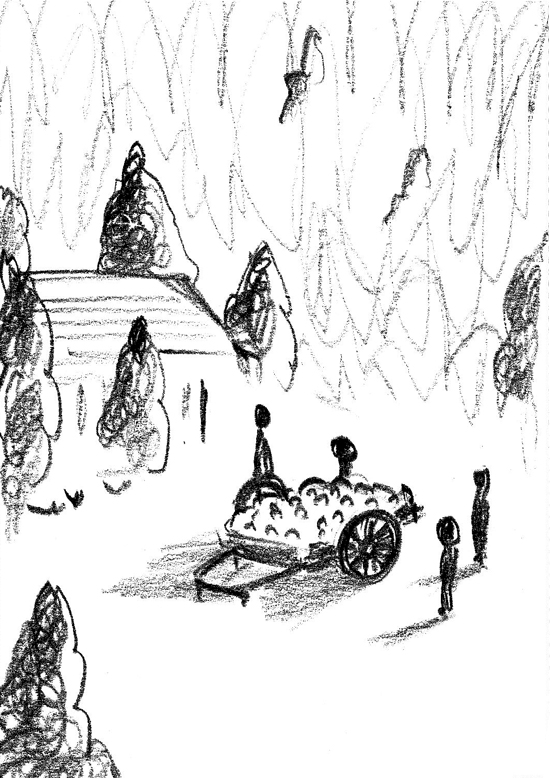
イラスト共に片桐 貞夫
しかし、名前は知っているかもしれない。
「青田チヨっていう名前を聞いたことありませんか」
「あ・お・た…いたなぁー。チヨっていうのは知らんが青田っていう名前は憶えとる」
「いた? 今はどこに…いえ、その子孫の人たちは」
電話帳にはなかったのだ。
「知らん。どうしたんじゃろなぁ、いつの間にか聞かんくなった。ずっと前のことだに」
「舟かたでしたか」
当時、寄居土着の人間は百姓か舟かたしかない。
「たしかそうじゃ…舟にのっとった」
美重子の胸がときめいた。
…チヨさんの家族だ。チヨさんの肉親だ…
「どこにいったか。ええ、その青田っていう家族なんですけど、知ってる人ありませんか。いえ私は、ちょっとした知り合いなんです」
美重子は言いながら高めてしまった語尾を弱めた。
《…なにをしようっていうの。チヨさんの家族を探し出して、いったいどうしようっていうの。過去は戻らない。チヨさんは故郷の土になったばかりじゃないの…》
自らの思いに美重子は顔をもどした。そして静かに首を横に振った。
「いえいいんです。すいませんでした」
身体をまわした。それから心の中で目を閉じた。
若いチヨが微笑んでいる。裾の短い絣の単衣を着て、恋人らしき若者と肩を寄せ合わせている。林立する松の合間に荒川の水が青い空を映していた。
「そうですか。そうなんですか…このあたりが『千本松』の林だったんですか」
美重子は目を細め、ひとりごとのように何度も同じことを繰り返した。
「ところで」と、野菜売りの老婆が山田夫婦の方を見て口調を変えた。
「去年、そこで死んだ人なあ…」
「………」
山田明子がうかぬ顔をしている。
「…あの爺さん、この村の出らしい」
「だれですか。なんのことですか」
たまりかねたように山田が言葉をはさんだ。「ほれ、あそこに死んどった人だに」
老婆が、意外そうに祠を指さした。
「知りません。知らないわなんにも。誰か死んだんですか・・あなた、知ってる?」
山田が夫の方にも顔を向けた。
「いや、知らん」
山田の夫も首を振った。
「知らん? そんな馬鹿な…このあたりは大騒ぎだった。あたしが仏さんを見つけたんだに」
「いつごろのことですか、去年の」
「たなばたよ。去年の七夕の朝よ」
「たなばた?…」
不意に上がった声は不破美重子のものであった。
去年のたなばたといえば青田チヨの死んだ日だ。山田明子がカナダに行き、その夫が東松山の長男宅に寄留している時であった。
「…どうして死んだんですか。だれです。どういう人なんですか死んだ人」
「自然死だそうです。九十以上の人でしたから。名前は忘れましたけんど、なんでも昔、人を殺して網走の監獄にいってたそうですに」
「だ・誰を殺したんです!」
美重子の声が震えている。
「いや、私が聞いたのは若い時、女のことで人を殺したっていうことだけで誰だか」
「………」
美重子は、頭を下げると祠の方に歩いた。一人になりたかった。考えなければならないことがありすぎると思った。
…若い時、女のことで人を殺した九十以上の老人が故郷に帰ってきた。そして青田チヨと同じ日に死んだ。去年の七夕の日…この祠の前で…
祠の前に一抱えもある縦長の石が立っている。長い歳月の風食で一部が欠損し判読しがたいが、「奉献」の上の達筆なひらがな文字は「ずきり」のようであった。
…チヨさんは、病気でもないのに食べることを止めた。七夕の十日前だった…
美重子は昨夜のことを思った。一人歩いた川原からの天の川の輝きを思い出した。それはかつて見たこともない煌々たるもので、眩しいほどの銀河の流れであった。
七、 天の川
カナダに帰った不破美重子のもとに山田明子からの封書が届いたのは、まだ十日もしない朝であった。山田は言う。
「ご要望の新聞記事を送ります」
美重子は、同封されてきた埼玉新聞の一部をコピーした紙片をつかんだ。
(続く)












