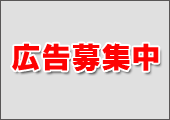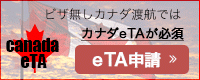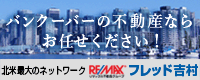昔、パリの絵描きがたむろしているモンマルトルの辺りをウロついていた時、十二月の風があまりにも寒くて、洋品屋に飛び込んでハンチングを買った。
それをかむったら頭が暖かくなって、ヤレヤレと思っていたら、同行の友人が、何となく地ゴロみたいだと云った。自分では似合うつもりだったがウィンドに写る己が姿を見たら確かにフランスのギャング映画に出て来て、すぐ撃たれて死んでしまうゴロツキのように見えるし、見方によっては馬が洗面器をかむったようにも見える。渋々そのハンチングはバックにしまい込んだ。
身につけるものは本人が気に入っていても、他人の目から見ると必ずしもそうではないので難しい。
日本に住まわれる西洋の方が日本の伝統的なお祭りなどでユカタを着ているのをよく見かける。日本にとけ込もうとする心意気が感じられ、ほゝえましく思うし、白人女性が見事に着物を着こなしている姿を見ると心がなごむ。
しかし総じて白人男性のユカタや着物姿は今一つである。これはどうにもならない日本人と西洋人の体形の違いからくるらしい。
もっとつきつめれば、それは大和民族と西欧人の足の長さの問題である。専門家でないから良くわからないけれど、どう努力しても西欧の男性が着物を着たとき締める帯の位置が高くなってしまう。それに日本人男性は下っ腹にギュッと帯を締めるから全体のイメージが極めて安定感がある。それに引きかえ西欧の男性は幸か不幸か腰骨の位置が高いのに帯を腰骨の上に締めるから帯を境にしたバランスが逆になってしまう。
なんとなく上半身に重みが集まってしまって北極の氷の下にいるクリオネのように見えるし、身体がひっくり返ってしまいそうで安定しない。下手をすると大人のダダッ子みたいに見える。
一方ジーパンはその逆である。西部劇の映画などで見るジーンズをはいたむくつけき男達は文句なしに様になっていて、皆一度はあこがれる。
西部劇のみならず、最近はかなりフォーマルな場にもジーンズを着用して訪れる人も多いらしく上半身は背広をはおっていてもあまり違和感がない。
元々ジーパンは作業衣だそうだが開拓時代からの歴史の匂いが感じられるし、ユカタと違って平均的に腰骨の位置の高い西欧人には文句なしに似合う。
それに大和民族と西欧人の決定的なマスクの造りも大いに影響している。限りなくバタくさい衣料なのだろう。
日本で暮らしていた頃は先ずジーンズは、はかなかった。その頃の日本ではジーンズはやはり作業衣と云うイメージが圧倒的に強かった。若い人なら許せるものの、多少なりとも威儀をたださなければならない場所にはなんとなくそぐわない。
職種にもよるだろうけれど少なくとも商談の場などには向かないとされていた。
二十数年前にカナダに移り住んで少なからず開放的な気分になってジーンズの上下を買った。早速街を歩いてみたり店のウィンド・ガラスに映る我が姿を横目で観察してみたりした。
しかし体にピッタリ合っている寸法のものを求めた筈なのに廻りをジーンズをはいて歩いている白人達とどことなく違う。
特別、寸詰まりの体ではないのに何となく違和感がある。どう気取って歩いてみても颯爽感がない。下手をすると、畑仕事を終えてホコリをはらって町に出てきた農夫のように見える。
十五年程前の寒い日にダウンタウンの店で、昔西部の開拓者デイビー・クロケットも愛用していたというラクーンの毛皮の帽子を買おうと思い頭にかむって鏡の前に立った。なる程かむってみれば暖かく釣りにゆく時も最適だと思った。決して安いものではないけれどタマには土地に根づいた物も身につけてみたい。ウシロの尻尾も愛敬。
しかし鏡に映る我が身を眺めた時、反射的に「コリャ駄目だ」と拒否反応が働いた。端的に図形的に云えば砂漠のラクダが頭に植木鉢をのせて笑っているとしか思えない。
でもそれだけではない。どこかで見たような人が立っている姿に似ているのだが、どうしても思い出せない。誰だろう誰だったかな…と考えながら帰りのバスに乗る。
家に着くまでボーッと外の景色を見ながら考え続けたが、それが誰だったかわからずに玄関のドアを開けた時、俳句のカレンダーが目にとまった。
悲しいかな、その謎の人物はかの奥の細道で名高い、俳人の松尾芭蕉だと気がついた。 帽子屋の鏡の中で笑っていたのは、およそカナダ西部の風土とは縁のない俳聖「芭蕉」だった。
自分に似合うものを見つけるのは事のほかむずかしい。
2011年10月27日号(#44)にて掲載