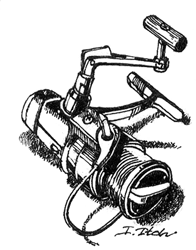
いつの頃からか解らないけれど、私は滅法魚料理が好きである。魚を食べるのもさることながら、生きの良い魚を見るのも大好きで、魚屋に並んでいる色とりどりの魚を見ているだけでもストレスの解消になる程である。創造主の作品である魚体の無駄のないフォルムに見とれてしまう。
幼い頃、郷里の小川でタナゴの数釣りをし、次から次へと虹色の体を輝かせて釣り上る大小のタナゴを見て、そのあまりの美しさに夢の中の出来ごとのように感動したのを思いだす。
長じて海釣りに走った。河の釣りとは違って驚く程のいろんな種類の魚が棲息する海の魅力に完全にとりつかれてしまった。だから河の釣りは、フナに始まり、タナゴ、ドジョウ、雷魚、うなぎ位まで進んで、そこでストップしてしまった。
魚釣りの一番遠くまで遠征?した経験は小笠原の父島でこの時は、湾内に停泊した客船の舟ベリからの夜釣りだった。竿も持たずに行ったので、夜皆が寝静まってからの糸を手に持っての脈釣りだった。結果は見たこともないヒゲの生えた センチ大の魚の大漁だった。人が「オジさんだ オジさんだ」と云うので、俺はまだお兄さんだゾ…と思ったら魚の名前だった。船の冷凍庫に保管してもらって東京まで持ち返ったが、冷凍を頼まれた船員がうんざりした顔をしたのを憶えている。たいした価値のある魚ではなかったのだろう。
日本で生活した頃は休日となると乗合いの釣り船に乗った。主に夏場の釣りで、東京湾で釣った魚は、その種類もさることながら、数が知れない。その中でも、木更津のカレイ釣り、第二海堡廻りのカサゴ、メバル釣り、平潟湾入口あたりのあなごの夜釣りは懐しい。
釣りが昂じて、とうとう廃船まぎわの18フィートのモーターボートを手に入れた。乗合船と違って、トナリに座った頑固なオッサンと糸のからみ合いでもめる心配もなくなった。天にも登るようなうれしさで東京湾を走り廻り休日には必ずなにがしかの釣果を携えて家に帰り、刺身、天ぷら、焼魚となって食卓に登った。
普段は仕事で朝早く出勤し夜おそく帰宅する。休日はやはり朝早く西洋の魚売りみたいな格好で大きなクーラーを背負って家を出て夕方家に帰るので、近所の人ともあまり顔を合わせる機会がない。ある時など隣家の小さな子供と顔が合って「アレッ おじさん来てたの?」と云われる始末。たまに来る旦那のようだ。「おじさんはこの家の人なんだョ…」と云ってこの骨太の子供を抱き上げた途端、腰のあたりでギクッと音がして第一回目のギックリ腰となり、一週間寝込んだ。確か5才位だったこのヒロちゃんという男の子は、ヤケに目方の重い子だったのを思いだす。
モーターボートを手に入れてからは、思いのままに狙った魚のいる場所に行ける。一人で釣行することが多かった。だから、トラブルが発生した時は機械音痴の私の口の中はパニックに動転してカラカラだった。一度、東京湾の荒れた日に釣りに出て信じられないようなトラブルに遭遇した。波間を漂っていた古いタイヤがスッポリとスクリューにはまってしまったのだ。そう云う時に限って緊急用の船外機のエンジンも動かない。これではどう考えても港に帰れないので冷たい波しぶきをあびながら気合いを入れてナイフでタイヤを切る作業に専念したが、どうしても切れない。タイヤにはワイヤーが沢山通っていることを初めて知った。やむなく投錨。
とうとう2メートルを越す波の中で、もまれるボートの船首に立って近くを通る船に両腕をいっぱいに伸ばして円を描く救助を求めるサインをだした。こんなことをしたのは初めてで恥かしかったけれど背に腹は代えられない。しかし朝の漁船は皆忙しそうで、誰も近寄って来てはくれそうにない。このままだと強い波風に錨がズルズルと動き、どこかの岸壁に…と思った時一隻の漁船が近づいて来た。
見れば若い20代の船頭で「どうしたい!」と風の合い間に声がする。これを見てくれと私が指をさすスクリューを見て「オラア 急いでんだヨウ!」と云いながら彼は、ロープを引きずり出している。やれ助かった。足の力が一気に抜ける。船首でその若い漁師が投げるロープを必死でボートのクリートに結ぶ。手がかじかんで思うように動かない。このまま港まで曳航してくれるらしい。
曳航してくれる漁船とボートの間は20メートルもあるので船頭の声が聴こえないまま走り出す。どっちの方向に帰りたいのか腕を大きく振りおろす手信号で知らせる。30分程猛スピードで曳航されようやく母港に着いた。そこは波も風も全くなく漁師の云う通り、ロープを外す。
「あと桟橋まで行けるだろう。わりいけどヨウ!」
そう云って若い漁師は全速力で去って行った。
「ありがとう!」
エンジンの音で私の声が彼に聴こえたかどうか。多分、仕事に行く途中の漁師だったのだろう。それなのに私の難儀を見過ごせず彼は助けてくれた。根岸湾を出てゆくこの青年漁師に爽やかな何かを教えられたようで知らず知らずの内に私は頭を下げていた。
さて問題はそのあと。どうやって50メートル先の桟橋までたどりつくか考えてしまった。エンジンはスンとも云わずこうなるとボートは唯の大きい箱である。苦肉の策でボートフック(物をひっかける長い棒)で水をかいた。2トンを越えるボートは50メートルを1時間かかって桟橋についた。冬だと云うのに汗びっしょり。
その翌週の日曜日、私は酒と菓子折を持って根岸湾に近いこの漁師の家を訪ねた。曳航されながら、かじかんだ手でメモした船尾の船名が頼りだった。漁師の家が並ぶ狭い小路を行ったり来たりしながら彼の漁師の家をようやく探し当てた。長屋のようなその軒の低い家は雨戸が締って誰もいなかった。これでは礼も云えず困ったなあと思っていたら路地の入口の方から小さな自転車に乗った女の子とその母親らしい買物カゴを下げた女性が唱歌を唄いながら近づいてくる。漁船の名前を云ったら、女の子が「トウちゃんの船だ!」と云ってうれしそうな顔をする。陽に焼けた歯の白い女の子だった。買物カゴの女性は目指す漁師の奥さんだった。
このあとの奥さんとの会話を実はもうあまり思い出せない。あまりにも昔のことだし、多分私は一所懸命頭を下げてご主人の親切に礼を云ったのだと想像している。でも、この奥さんが私のささやかなお礼の品を受取った時「わりいネ…」と云った一言が不思議に忘れられない。それは青年漁師が私のボートとのロープを外した時に云った最後の一言と同じだったから。
2007年4月19日号(#16)にて掲載












