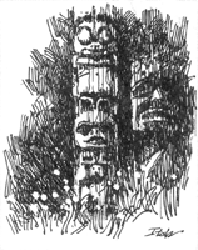
〈前回より続く〉
私は15年前に日本からカナダに移り住みました。それ以来、カナダ西海岸の自然が豊かな風景画を描き続けてきました。しかし3年前の12月、私はストロークに見舞われました。病院に搬ばれ、一週間後に5時間に及ぶ手術を受け、幸いなことに手術が成功して元の身体に戻ることができました。
脳溢血で即刻亡くなる人が多い中で、私はとてもラッキーでした。手術をして下さったドクターに勿論感謝しているけれど、私は今考えるとやっぱり目に見えない何かの加護があったのだと思っています。 それ以来、全く元の身体に戻った私は再び絵を描き、大好きな魚釣りを楽しんでいます。手術後に釣れた魚も数知れません。これからもこの貴重なカナダの自然のフトコロで暮らすことを私は許されたのだと思っています。ありがとう。
燃えさかる石の暑さで汗みどろになりながら、私はたどたどしい言葉でこんな事をしゃべった。思いもかけず、居並ぶ先住民たちの間から大きな喚声が上がった。「ウォーッ」「ひゃーッ」という声と共に、打ち鳴らされる太鼓の音も一段と大きくなった。ああ、この人たちは私のストロークからの回復を喜んでくれている・・・と思った。今日初めて会ったばかりだというのに・・・。そう考えたら、突然胸に熱いものがこみ上げてきた。私にとっては不意打ちの喚声だった。暑さによる汗と不覚にも溢れ出た涙で周囲が見えなくなってしまった。
スピーチは若いネイティブのところに順が進んだ。この女性は家族に老人がいて、その老人の病気の回復を神に祈っているようだった。涙ながらに鼻をすすりながら話す言葉から察するに、その老人は彼女の母親ではなかったのだろうか。
私は目をつむったまま、3年前のストロークのパニックを思い出していた。それは暮れも押し迫った12月17日の朝、私を突然襲ったパニックだった。食事を終えて立ち上がり「さあて今日は・・・」と腕を上にあげて伸ばした時、頭のウシロの方でプツンという小さい音がした。目の焦点が合わなくなった。次に眩暈(めまい)がして立っているのが辛くなり、ロレツが廻りにくくなった。「来たな!」と思った。
しかし幸い頭はしっかりしていた。救急車がくるまでの15分の間、ベランダで干物にするべく網にのせて干しているカレイを取り込むことをワイフに指図した。二日前の漁獲だった。一刻を争うような時なのに、我ながら口うるさい病人だと思った。
横になったまま、手術まで1週間待った。いろいろな検査を受けた。中でも頭をスキャナーで撮影された時の頭の中のスクリーンに展開される衝撃的な映像はこれまで見たこともないような美しさだった。多分、脳の中の患部を正確につきとめるための、X線による撮影と思われるその検査は約5分間横になったまま微動もできないものだった。
しかし、その検査が始まった途端、まるで巨大なオーロラを見るような、又最も前衛的なコンピューターグラフィックスの作品を見るような動く映像が全天に展開された。あっと驚くような見事な色彩だった。輝くイルミネーションのようなブルーのモアレ。サイケデリックなピンクとパープルカラーの放射状の光。夜空の星がいっせいに花火になって開いたような幻想的な光の重なり。思い出してもゾクゾクするような一大ページェントだった。たった5分間で終わってしまったのが、惜しいくらいの体験で、お金を払ってでももう一度見たい素晴らしい光の乱舞だった。
12月24日、クリスマスイブが手術の予定日だった。病院で出される食事は正直なところ全く喉を通らなかった。まず、全然食欲がないことに加えて、私が最も苦手とするミルクが使われている流動食が多く、とても手が出ない。入院以来、水しか飲まずに手術の日を迎えることになった。体力がドンドン落ちてゆくのが自分でもわかった。嫌な感じがして、しぶしぶ親戚には連絡してもらわざるを得なかった。
手術の直前に担当の脳外科医の名前を聞いた。「日系の脳外科の専門医」だそうで、飛び上がるほどうれしかったが、飛び上がれるような体力はもうなかったのが事実である。しかし、そのあとに医師の名前がDr. Akagamiと告げられ、次第に意識が薄れ気が遠くなってゆくのを感じた。昔の日本の軍隊の召集令状「赤紙」という文字が頭を去来し、薄れる意識の中で、どこに召集されるのだろう・・・などと思った。
そんな思い過ごしも手術後の麻酔からさめた時の爽快さが吹き飛ばしてくれた。手術から二日しかたっていないのにすききった胃が食べ物を猛烈に要求する。自分の好きな食べ物があとからあとから、まどろむような夢に登場する。
カツ丼、うな丼がUFOのように飛んでくる。天丼も斜めになって飛来するし、焼きそばなどはグルグル廻りながら、湯気をたてて目の前を通り過ぎる。
病院の食事だけではとても足りなくなって、とうとう中華レストランから焼きそばを買ってきてもらった。発泡スチロールの容器に入ったその広東風焼きそばのボリュームに圧倒される。どう見ても二人前で、いくら何でもこれは食べられないから、残りは家に持ち帰って食べてくれ・・・とワイフに言ったものの食べ始めたら箸がとまらなくなり、全部平らげてしまった。ドクターアカガミに唯々感謝をしながら、差し入れの日本食を味わい大晦日の退院となった。手術後1週間だった。翌日は元旦だった。この朝飲んだ日本酒の味は忘れようにも忘れられない。このとき初めて、「俺は助かったんだ・・・」と思った。
そんなことを思い出している間に神への祈りは第一ラウンドを終わった。熱気で頭はもうろうとし、外に出たい衝動にかられる。鳴り続けていた太鼓が止んで、テントの外から出口の毛布がはね上げられた。ヨロヨロと這うように外に出る。相変わらず石を燃やす焚き火が大きな炎を上げている。大木の切り株に腰をおろしたものの、テント内の暑さで平衡感覚がマヒしたのか、切り株から横にころげ落ちる。あわててそばを流れる巾4メートル程の小川に飛び込む。その水は骨がきしむほどの冷たさだった。
こんな儀式のラウンドがテーマごとに4回繰り返された。
祖先、肉親、万物の霊への祈りなど。ついに私は3ラウンドでギブアップ。4ラウンド目はパスさせてもらった。4ラウンド目の儀式が行われている間、外の焚き火が消えないよう薪をくべ、燃える石をテント内に運ぶネイティブの人たちと話をする機会が持てた。それは連綿と続く彼らの長い歴史をわずかながら私に垣間見せてくれた。話そのものが宗教の法話のようであり、サウナの儀式で悪霊が追い出されてしまったような私の身体に吸い込まれてゆくようだった。
〈次回に続く〉
2006年11月30日号(#49)にて掲載












