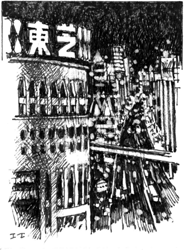
私が世の中に出て、はじめての仕事場は東京の銀座だった。夢と希望で胸を一杯にして会社づとめを始めたものの、現実の社会には想像もしていなかったような、つじつまが合わないことが沢山あることが少しずつわかってきた。
そんな矛盾にどうにも頭が整理できなくなって、会社のトイレに入りくやし涙を流したのもこの頃だった。
デザインと云う仕事は形や色彩以前に絶えず世の中の流行や世相を把握していないとアッと云う間にとりのこされてしまう世界で、駆け出しの青二才にとってみれば背筋が寒くなることもある反面、自分が創りだした作品が認められて巷で人の目に触れることになった時のうれしさは何にも替えがたいものだった。
緊張が連続すると人は誰でも息を抜きたくなるもので資料探しを理由に会社から十分歩いて銀座通りをブラブラすることが多かった。
日本を代表する繁華街の銀座は当時、柳も健在で一種の風格があって例え雨の日でも仕事にほんろうされ、痛めつけられたポッと出の青二才の心をなぐさめてくれた。
あるとき東銀座から西銀座の数寄屋橋まで足を延ばし欄干にもたれて、夕暮れの川面を眺めていた。たそがれ時の日劇のネオンが水面にゆらぎ、にじむようであゝこれが都会の美しさなんだなあ…と柄にもなく「哀愁」のようなものを感じた。
時間も遅かったし、もう社に戻らずこのまま家に帰ろうと思ったけれど、電車に乗る前にちょっと腹ごしらえ…と思って日劇の近くの甘味屋に入った。ラーメンも旨い店だったので相席のイスに腰かけてラーメンを注文した。
ふと向い合ってお汁粉を食べている女性を見ると鼻をすすりながら食べている。舞台衣裳の上にコートを羽織っただけの日劇の踊り子だった。
当時、売り出し中のダンシングチームの中では、脚光をあびていた踊り子でなぜか泣きながらお汁粉をたべている。
年代が近い気楽さでラーメンを啜りながら、「アノどうかしました?」と聴いた私に彼女が下を向いたまま恥ずかしそうにポツリポツリと話した。
私には踊りの事はわからないけれど煎じつめれば舞台監督にかなり屈辱的な言葉をあびせられたらしく、良く聴くような話だと思った。
その舞台監督は私も知っていて激情型の人と聞いた。まあ悪い人じゃないんだろうから…となぐさめた。
自分もその頃上司にこっぴどく仕事のヘマを罵倒されることもあったので、デザイナーも踊り子も何だか同じようなものだなあと思った。
今はもう無くなってしまった日劇ミュージック・ホールの道を隔てた向い側にビヤ・ホール、ニュートウキョウがある。脇の道を入って突き当り、右に折れると私の好きな焼キトリ屋が軒をつらねていた。
アイ・シャドウが流れて狸のような顔をした彼女が一生に一度でイイから豚モツの焼キトリ屋に行ってみたいと云った。大ゲサだな…と思ったものの考えてみれば若い女性が一人で焼キトリ屋で飲んでいるのを確かにあまり見かけたことがない。
安サラリーマンで、おまけに居酒屋党だから時には昼メシ代にも事欠いていた私だったが、ある日給料日に舞台がはねたあとの彼女を有楽町ガード下の焼キトリ屋に騎士道を発揮して案内した。
仲間のダンサーを二人連れてきた。身体を使う人達だからよく食べる。懐が一気に涼しくなった。
フランク永井が唄う「有楽町で逢いましょう」が大ヒットしてから間もない頃で、百貨店のコマーシャル・ソングとも知らず、この歌に惚れ込んでいつも口ずさんでいた。
あなたを待てば雨が降る…濡れて来ぬかと気にかかる…有楽町、数寄屋橋かいわいのたたずまいは何故か雨が似合う雰囲気があった。
中でも雨に煙る日劇ミュージックホールの夜の灯りは、どんなに派手なネオンをつけても雨ににじんでメランコリックな情感があって、これはクラシックな建物からくるものだったのかもしれない。
数寄屋橋かいわいは土地柄もあって昼日中から芸人が歩いているのをよく見かけた。当時、人気上昇中の漫才師獅子てんや、わんやご両人が、何がおかしいのか脇腹をツツキ合いながら歩いていたり、歌手灰田勝彦氏を日本そば屋で見かけたのもこの頃。
そうかと思えば、ベレー帽をかむって本を抱えて歩く手塚治虫さんとすれ違ったりする気さくな雰囲気の街だった。
たまに日本に行くと足がどうしても有楽町、銀座界隈に向く。もう数寄屋橋は名が残るだけだし、日劇も無くなった辺りに立ってあの頃の自分を思い出したりお汁粉を食べながら泣いていた踊り子は今頃どこでどうしているだろうと、フッと思ったりする。
昭和が歴史の霧の中に消えてゆく。
2010年5月27日号(#22)にて掲載












